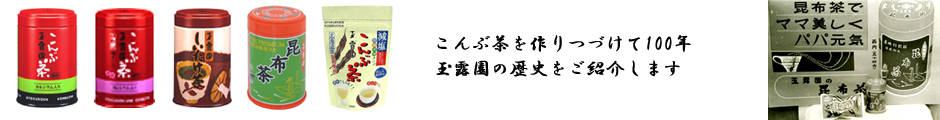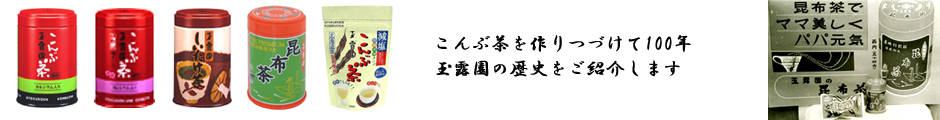まずは味の良い昆布を見つけなければならない。馬三は東北、北海道、樺太(現ロシア連邦サハリン州)へ向かう旅に出て、海岸線沿いにくまなく昆布を探して歩いた。
汽車の中では入手した昆布を噛み続け、宿では煮汁を濃くしたり薄めたりして嘗めたという。
その結果、馬三は北海道知床岬の付近で採れる、羅臼産の昆布を使う事に決めた。ここで採れる羅臼昆布はリシリ系エナガオニコンブとも呼ばれ、
繊維質が軟らかく、香りが非常に良いのが特徴。だしはもちろん、高級塩昆布や煮昆布としても使われる最高級品だった。
東京に帰った馬三は寝食を忘れて昆布だしの採り方を研究し、入手した中から最も飲み物に適した昆布を探し当てた。
その昆布を薬研にかけて粉末にし、更に塩、砂糖などの調味料の配合を検討。何もないところから新たな商品を生み出すのは簡単な事ではなかったが、
1918(大正7)年、ついに念願のこんぶ茶を作る事に成功した。
最初は個人商店での細々とした商売だったが、これが大成功。「今までの昆布茶よりずっと美味しい」「お湯を注ぐだけで飲めるのに、味わい深い」と、
その品質が高く評価されたのだ。何よりも馬三を勇気付けたのは、お茶の好みがうるさい東京人に支持された事だった。
この時期の多くの商売人たちと同様、馬三もまた、1923(大正12)年の関東大震災と45(昭和20)年の太平洋戦争敗戦によって、大きな打撃を受けている。
それでも、震災後の30(昭和5)年には東京・神田に新たな拠点「玉露園」を開店し、こんぶ茶だけでなく、
粉末茶の新商品「宇治グリーンティー」(後の「玉露園グリーンティー」)を販売した。
この頃、馬三はこんぶ茶を全国ルートに乗せるため、既存のお茶屋との間で「お茶(日本茶)を扱わない代わりにこんぶ茶を置いてもらう」という契約を結んでいる。
それでいながら玉露園という商号を付けたところが、馬三のしたたかなところだ。更に35(昭和10)年には「のり茶」を販売。
この頃になると同じような昆布茶を売る同業社もあったが、既に玉露園は他社の追随を許さないトップメーカーとなっていた。
ちなみにお馴染みの赤い缶は、最初の頃から使われているこんぶ茶の大切なアイデンティティー。今もしっかり守られている。
馬三のこんぶ茶にかける情熱が伝わってくるエピソードがある。
太平洋戦争の戦局が拡大し、様々な経済統制法が施行されると、当然ながらこんぶ茶も製造する事が難しくなった。
ところが慰問品用として昆布茶が喜ばれた事もあり、多くの同業他社は代用原材料を使って品質の劣った製品を作り続けた。
それでも作れば金になるし、何も作らなければ会社は困窮する。が、このとき馬三はこんぶ茶の製造をきっぱりと諦めた。
「今、信用を落としたら、戦争が終わった時に商売を再開できないかもしれない」そんな思いがあったのだろう。
戦後、バラックのような小屋で馬三が再びこんぶ茶を作り始めた時、戦前戦中の得意先はこぞって歓迎してくれた。
「玉露園のこんぶ茶、只今入荷!」という貼り紙が小売店の店先を飾り、お客がどんどん集まった。消費者もまた、玉露園のこんぶ茶との再会を待ち望んでいたのだ。
|